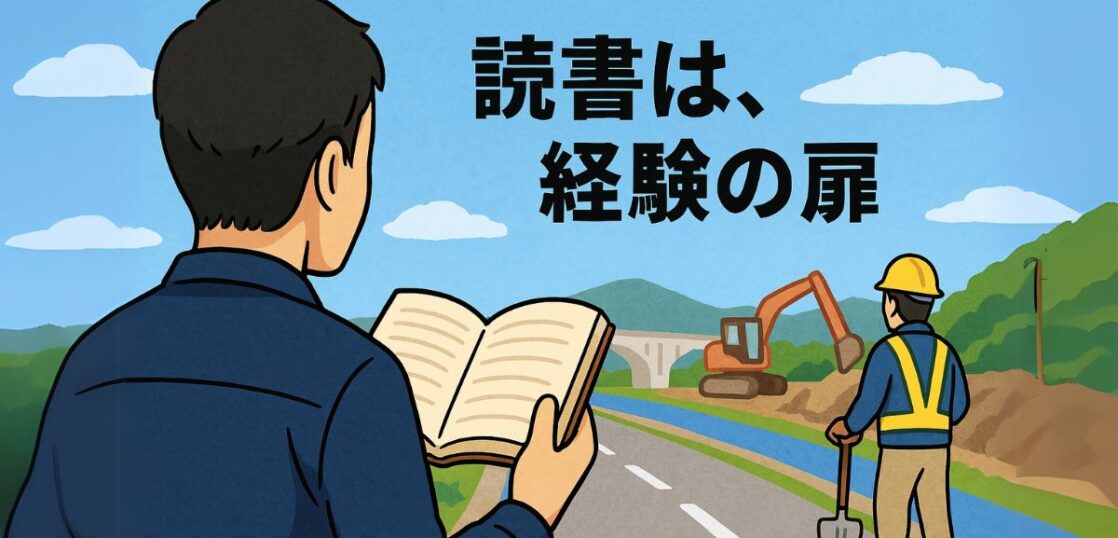読書は、経験を超えるチャンス
「本を読むって、何のためですか?」
そんな問いを、若い社員から受けたことがあります。
少し前の私なら「知識を得るため」と即答していたかもしれません。
でも今の私は、少し違った答え方をします。
「読書は、自分が体験できないことを、代わりに体験できるチャンスだよ」と。
私たちは、自分の人生の中で出会える人や経験できることには、どうしても限界があります。
時間、場所、立場、役割。
どれだけ努力しても、すべてを体験することはできません。
だからこそ、本がその“限界”を軽やかに飛び越えてくれる存在になるのです。
歴史小説を読めば、時代を越えて過去を生きることができる。
哲学書を読めば、自分とはまったく違う価値観と対話できる。
経営書やエッセイを読めば、著者の思考の裏側を追体験できる。
まさに読書は「他者の人生を生きることができるツール」だと感じています。
多様なジャンルは、多様な“自分”をつくる
私はどちらかといえばビジネス書を読むことが多いですが、たまに意識して小説やノンフィクション、時には詩集のようなものにも手を伸ばします。
ジャンルが変わるたびに、得られる視点もガラリと変わります。
たとえば、経済の本からは「構造的な思考」を。
小説からは「人の心の機微」を。
旅行記からは「風土と文化に根差した価値観」を。
そしてエッセイからは、「日常を深く味わうまなざし」を学びます。
そうやって、さまざまなジャンルに触れていくと、まるで自分の中に“別の人格”や“別の視点”が育っていくような感覚になります。
日常の中で何かに直面したとき、
「もしあの著者だったら、どう考えるだろう?」
「小説の登場人物なら、どんな行動をとっただろう?」
そんな“対話”が、自分の中に自然と生まれるのです。
これは仕事でも同じです。
一見、土木や現場仕事とは関係のないジャンルの本でも、意外なところでインスピレーションをくれたり、社員との対話に深みを持たせてくれたりします。
関係ないジャンルの方や、今まで自分自身が読んだことのないジャンルを読む方が、多くのものを得られるチャンスがあるなと思います。
読書で深まる、自分自身の“軸”
情報があふれる現代では、「知識」はすぐに手に入ります。
検索すれば、答えらしきものは簡単に見つかる。
でも、そこに「考える力」や「選びとる力」がなければ、情報はただ通り過ぎていくだけの存在になってしまいます。
読書というのは、知識を“通過”させず、自分の中に“蓄える”ための装置です。
読みながら考える。
読んだあと、少しぼんやりと思いを巡らせる。
それによって、自分なりの軸や判断基準が育っていく。
たとえ内容を全部覚えていなくても構いません。
1行でも心に残れば、それはきっとその人の人生を支えてくれるものになる。
だから私は、今日も1冊の本を開きます。
「知らないことを知るために」ではなく、「もっと深く、自分と向き合うために」。
読書は、自分の内側を広げる旅です。
そして、その旅の積み重ねが、
仕事にも、人間関係にも、生き方にも、豊かさをもたらしてくれるのだと思います。
今日もブログを読んでいただきありがとうございます
関連記事、人気記事はこちら!
読書感想文もSNSも共感してもらえるために自分の想いを伝えることが大切!